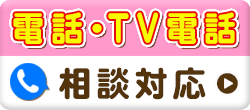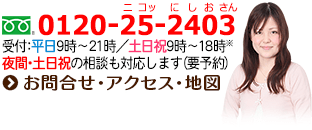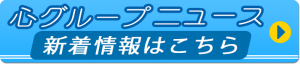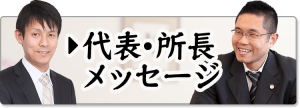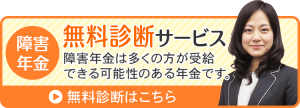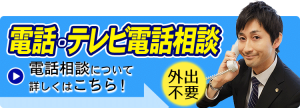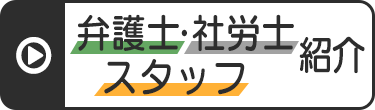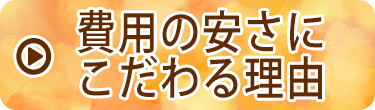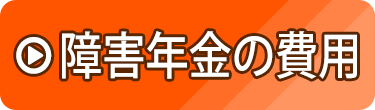精神疾患について障害年金が認められる基準
1 精神疾患の方も障害年金が受給できます 2 精神障害についてはガイドラインが制定され整備されてきています 3 支給対象となる精神疾患 4 精神疾患で申請する際のポイント 5 障害等級を取り消された場合にも異議申し立てができます 6 精神障害による障害年金の申請等でお悩みの方は専門家に相談しましょう
1 精神疾患の方も障害年金が受給できます
障害年金の法律上の受給要件は、主に以下の2点です。
・障害が残存していること。
・保険料の納付要件を満たすこと。
障害が残存しているかどうかは、国が定める等級基準を満たすかどうかによって決まりますが、その等級基準においては、精神疾患についても定められています。
等級は1級・2級とありますが、精神疾患の基準はいずれも「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」とされています。
前各号とは身体障害に関するものであり、それと同程度以上の程度ということですから、大まかに言えば、1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、2級は、「日常生活に著しい制限を受けるもの」ということになります。
精神疾患により、これらの状況にある方は、障害年金が受給できる可能性があります。
2 精神障害についてはガイドラインが制定され整備されてきています
以前は精神障害の認定については基準があいまいであり、地域によって認定の違いがあり不平等が生じていることが指摘されてきました。
こうした地域間格差をなくすべく、厚生労働省において専門家検討会が設置され、精神障害の認定について基準をより詳細にするためのガイドライン(精神ガイドライン)が策定され、2016年9月から施行されています。
精神ガイドラインでは、以下の具体的な5つの項目を示し、各項目に点数を付して、その総合判断により障害認定を行うことを定めています。
①現在の病状または状態像
②療養状況
③生活環境
④就労状
⑤その他
同ガイドラインでは、上記①~⑤の各項目についてさらに細かい考慮要素を示していて、そうした要素ごとの点数を総合して考慮することによって、障害年金1級、2級の認定を行うことが定められています。
3 支給対象となる精神疾患
精神疾患で障害年金を申請する例としては、うつ病、双極性障害、統合失調症、知的障害等が多くなっています。
また、てんかんも精神疾患として障害年金を申請することができます。
適応障害等のいわゆる神経症の分類に属する精神疾患については、原則として障害年金の認定対象となりませんが、症状が精神病の病態を示している場合には認定対象となります。
4 精神疾患で申請する際のポイント
精神疾患の症状は見た目では分からないため、精神疾患で障害年金を申請する場合には、日常生活や仕事をする上でどのような困難があるかを具体的に医師に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。
特に、仕事をしている場合には、1日の勤務時間や仕事の内容、勤務先にどのような配慮をしてもらっているか、障害者雇用か等を伝えることも必要です。
また、精神疾患の方は転院を繰り返している人も多いため、通院歴を思い出して整理することも必要になります。
5 障害等級を取り消された場合にも異議申し立てができます
精神障害による障害年金については、数年ごとに更新することと定められることが多いです。
認定後に就労しはじめた場合などには、障害年金の更新時に、働けていることなどを考慮されて支給が停止されてしまうこともあります。
しかし、相当程度の援助を受けて働いている場合には障害年金を受け取れる可能性があり、実際に働きながら障害年金を受給している方は多くいらっしゃいます。
働きながら障害年金を受給できる場合については、こちらのページで記載しておりますので、よろしければご覧ください。
もし、障害年金の支給が停止されてしまった場合でも、その決定の合理性に疑問がある場合や、上記の精神ガイドラインに則っていないなどの場合には、異議申し立てをして争うことができます。
6 精神障害による障害年金の申請等でお悩みの方は専門家に相談しましょう
精神障害は身体障害と比較すると目に見えないものであり、判断が難しい障害です。
障害年金の認定が受けられるかどうか、その判断は非常に難しいです。
しかし、精神障害については国もガイドラインを定めるなどして積極的に取り組んでおり、精神障害による障害年金を受給できる可能性は十分あります。
障害年金を受給できるかどうか、また、申請するにはどうすれば良いかお悩みの方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- ダウン症で障害年金を受給するためのポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
0120-25-2403