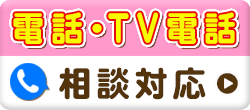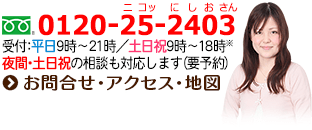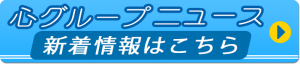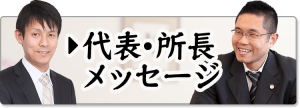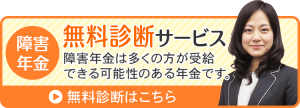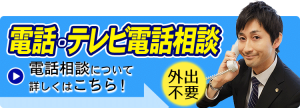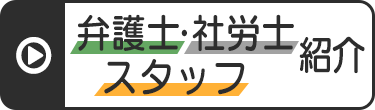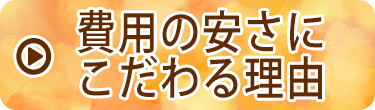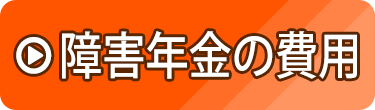障害年金の申請は自分でできるか
1 障害年金を自分で申請することの難しさとは
障害年金の申請をこれからしようと考えて情報収集を始めたり、実際に障害年金の申請の準備を始めたりすると、障害年金を自分で申請することの難しさを感じられる方もいらっしゃると思います。
そのように一般の方がなんとなく感じる「難しさ」を、障害年金申請のサポート業務を数多く行ってきた経験からもう少し具体的に言うと、「手続きの煩雑さ」「適切な診断書を書いてもらうことの難しさ」「結果を予想することの難しさ」に分けられると考えられます。
この記事では、これらの点について、具体的に掘り下げてお伝えしたいと思います。
その前に、まず整理しておきたいのは、年金制度全体から見た障害年金の特徴です。
公的年金制度から支給される年金には、障害年金の他に老齢年金と遺族年金があり、老齢年金は原則として65歳になったときに一定の要件を満たせば受給でき、遺族年金は配偶者や親が亡くなった場合に一定の要件を満たせば受給できます。
老齢年金と遺族年金の受給に必要とされる一定の要件は、年金の加入記録等から客観的に確認できる場合が多く、専門家のサポートに頼らなくても年金事務所で手続きできることがほとんどです。
しかしながら、障害年金の申請には、老齢年金や遺族年金とは一線を画するほどの難しさがあります。
そのため、申請をすること自体は自分でできますが、適切な書類を用意して適切な等級の認定を受けるためには、専門家のサポートが必要となる場面が多くあります。
2 手続きの煩雑さ
障害年金の申請を行うには、初診日を証明することが必要です。
初診日から長い時間が経過している場合や、転院を繰り返している場合は、初診日を証明するために時間と手間がかかることがあります。
また、病歴・就労状況等申立書という自己申告書を作成する必要があり、初診から(先天性の障害の場合は誕生時から)現在まで、いつ、どの医療機関をどのような症状で受診し、どんな治療を受けたか、その際の日常生活や就労状況はどのようであったかを記載しなければならず、これにも時間と手間がかかります。
煩雑さのために途中で挫折してしまっては、当然障害年金を受給することはできませんし、申請するまでに時間がかかれば、早く申請すれば受給できたはずの障害年金をもらい損ねてしまうこともあります。
3 適切な診断書を書いてもらうことの難しさ
障害年金の診断書には8種類の様式がありますが、そのうち7種類がA3サイズの表裏両面となっており、記載が必要な項目が非常に多いです。
そのため、診断書の作成は医師にとって大変手間のかかるものであり、記載漏れも頻繁にみられます。
場合によっては、等級の認定に直結する大事な項目の記載が漏れていることもあります。
また、医師は普段治療のために診察をしており、障害年金の診断書を作成するために診察をしているわけではありません。
そのため、診断書を作成するために十分な情報を医師が把握していないことが多く、診断書に記載された症状の重さと実際の症状の重さが一致しないということが起きがちです。
4 結果を予測することの難しさ
初診の医療機関にカルテが残っていない場合、様々な手段で初診日を証明することになりますが、どのような資料を提出すれば初診日を証明したことになるのか、一般の方が判断するのは困難です。
また、作成された診断書を提出した場合に、認定基準に照らして何級に認定されそうなのか、あるいは不支給になりそうなのかといったことも判断するのが困難です。
そのため、作成された診断書の記載内容が実際の症状を適切に反映したものなのかよく吟味せずに、そのまま提出してしまうことになります。
また、一般的に、年金事務所の窓口で等級の見込みについて教えてもらうことは困難です。
5 専門家が関与する意義
上記2~4で述べた難しさに対して、障害年金の申請を専門家がサポートする意義は大きく分けると、①手間がかからず手続きが早く進む、②適切な診断書で申請ができる、③障害年金が支給されるか、何級に認定されるかの見通しが分かることであるといえます。
実際に、障害年金を自分で申請して不支給になり、不服申立て(審査請求、再審査請求)をしたいというご相談を多くいただきますが、そのほとんどが適切な診断書等の書類を提出していない場合や、申請の方法が適切でない場合です。
残念ながら、そうした場合には不支給という判断はやむを得ませんし、不服申立てしてもうまくいく見込みはほぼありません。
また、再度申請をしたとしても、場合によっては既に提出した診断書等の書類の内容を理由に、また不支給となってしまうこともあります。
したがって、結果が出てから後悔することになるよりは、申請前に一度専門家に相談されることをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金の申請は自分でできるか
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を申請する場合のポイント
- ダウン症で障害年金を受給するためのポイント
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 肺線維症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
0120-25-2403