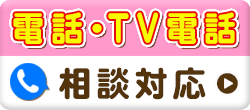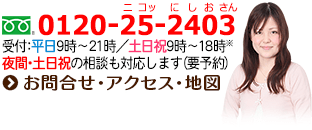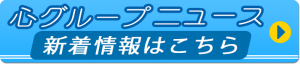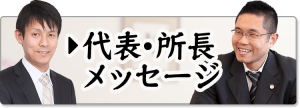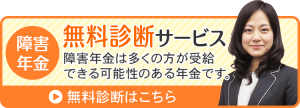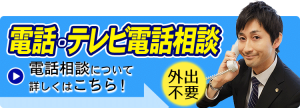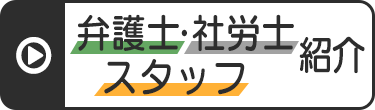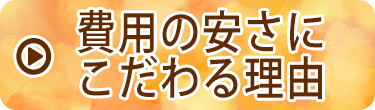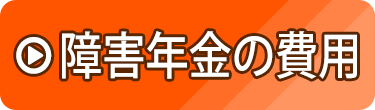てんかんで障害年金を申請する場合のポイント
1 てんかんも障害年金受給対象です
てんかんについても、障害年金受給の対象となっています。
こちらの記事では、てんかんで障害年金受給の申請をするにあたって、ポイントとなる点などについてご説明したいと思います。
2 抑制されている場合は原則として対象外であることに注意
てんかんの場合の障害年金の認定基準は、「てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。」とされています。
お身体にとってはよいことと言うべきですが、抗てんかん薬等で症状がうまく抑えられている状況では、障害年金受給はできないことになっておりますので、まずはこの点をご注意いただくとよいかと思います。
3 てんかんの認定基準
⑴ 発作の4タイプ
認定基準では、てんかん発作について4つのタイプに分類し、頻度等を踏まえて各等級の基準としています。
具体的には以下のA~Dです。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
⑵ てんかんの等級
てんかんで等級が認定される場合、各等級に相当すると認められる例は、以下のとおりとなります。
1級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの
⑶ 認定基準から読み取れること
例えば、2級の認定基準からすると、AかBの発作は年に2回以上の発生、CかDの発作は月1回以上の発生という基準にしていることからA、Bの発作と、C、Dの発作で分け、相対的にA、Bの発作を重いものと捉えていることが分かります。
「十分な治療にかかわらず」という記載からは、上記2のとおり、治療によって発作が抑制されている場合には認定基準を満たさないと判断されることが読み取れます。
4 発作間欠期の状態も判断要素とされる
上記3で引用した認定基準の記載のとおり、認定基準は、単に「てんかん性発作のA又はBが年に2回以上発生しているもの」となっているわけではありません。
てんかんは、多彩な症状が発現するため、発作の回数だけで単純に傷病の程度を決められるものではないといえます。
そして、発作がない間欠期においても、精神症状、認知障害等が発生することが少なくないため、認定にあたっては、発作間欠期における生活状況も重要な要素となってきます。
医師に診断書の作成を依頼する際には、発作の程度だけでなく、発作間欠期の生活状況等についても十分理解してもらうことがポイントです。
5 てんかんの障害年金申請をする際には専門家へ
このように、てんかんで障害年金の申請をする際には、気を付けるべきポイントがいくつか存在します。
それらの要点を抑え、適切な等級が認定されるように申請準備をしていくためには、社労士や弁護士といった専門家のサポートを受けることがおすすめになります。
私たちもそのようなサポートを行っており、てんかんの申請サポートを行った実績もありますので、てんかんで障害年金の受給を希望される場合には、まずは私たちにご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金の申請は自分でできるか
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を申請する場合のポイント
- ダウン症で障害年金を受給するためのポイント
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 肺線維症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
0120-25-2403